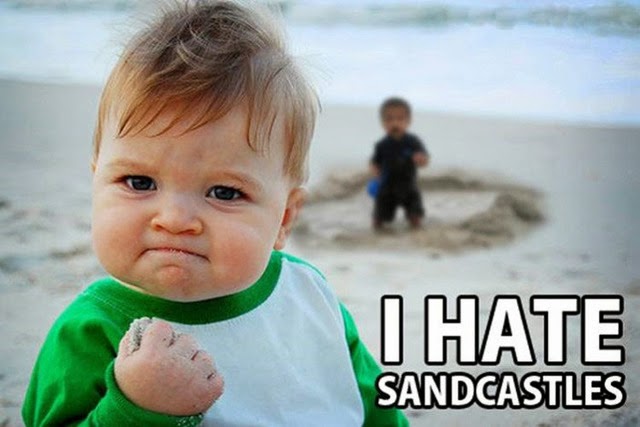何かをしてもらうことに慣れると、気付かないうちに依存体質になってしまいます。
先日生徒さんにこんなことを言われました。
「この教室って緊張感ないですよね」
そうなんです。認めます。
うちの教室には緊張感はありません。
私自身にもさほど緊張感はありません。
でも、その言葉を聞いた時に、この問題の根深さを考えました。
子どもたちの多くが、誰かに緊張感を持たせられなければ緊張感を持てない状態にあるということです。
そしてそのことに生徒本人が気付いていないのです。
このことは、その後教室の方で授業形式でお話ししました。
ちょっと心配だったので。
誰かに、何かに依存している人は、その自分の依存状態に気付かないことが少なくありません。
そして、周囲もそれを望み、普通のことだと思ってしまっている節があります。
例えば、わかるまでできるまで徹底指導します!と謳う塾などがそうです。
塾は勿論点数を伸ばし成績を上げるサービス業なので、それを顧客である保護者の皆さんは望みますし、そうやって何から何まで手取り足取りでやってもらえる方が生徒も楽でしょう。
だから大手塾も緊張感を煽り、カッコいいキャッチコピーで集客を図るわけです。
でも、私は、そこにすごく違和感を感じてしまいます。
オリジナルテキストを配り、授業をし、宿題を出して、できれば褒め、できねば叱り、緊張感や焦りを煽って「あと何日!あと何日!」とケツを叩く塾が多いのが現状なのですが、私からすればそんな勉強の仕方はまるで家畜と一緒にしか見えないからです。
進撃の巨人の観過ぎだと思われるかも知れませんが、そんな風に、自分で考えもせずに出されたものを次から次へと消化するだけなら、それは家畜です。
そして、それを保護者の皆さんや生徒さん自身が望んでいるかも知れませんが、社会はそんな教育で育った人間など望んではいないのです。
それが塾が現実社会と乖離している一番の原因です。
そして、塾が一教育機関として明確な認識を持たれている以上、その乖離はダイレクトに子どもたちに影響します。
結果、現実と乖離した若者が育つのです。
生徒さんには話をしましたが、誰かに緊張感を持たせられないと自分を奮い立たせることができないままでは、その他大勢にしかならないし、その他大勢にしかなれない勉強に意味はないと説明しました。
この教室は決して手取り足取りはしないし、こっちは手を差し伸べて待ってるだけで、掴んでくれたら引っ張り上げるけど、こちらから掴みに行ったりはしないよ、と。
だから、緊張感はないけど、実は結構厳しい環境だったりするんだよと説明しました。
それから、皆は「自分はできるのにできないだけだ」と考えてほしいと伝えました。
前提を間違ってはいけないと。
「自分はできない」ではなく、「自分はできるはずなのに、どうしてできないんだ??」と考えることで、具体的な阻害要因除去の思考が働きます。
この差が実はでかいんです。
今の子どもたちに、本来の「自分が今勉強している意味」に気付いてもらえるよう、もう少し発信していかねばなと感じた出来事でした。